1995年に公開されたデヴィッド・フィンチャー監督作『セブン』は、公開から30年近くが経った今もなお語り継がれるサスペンス映画の金字塔です。鬱屈した都市の空気感、重厚な映像美、そして息を呑むようなラスト――その全てが観客に深い衝撃を与え、映画史に刻まれることとなりました。
特に本作を象徴するのは、犯人ジョン・ドウの存在です。彼が仕掛けた「七つの大罪」をモチーフとする連続猟奇殺人は、ただの快楽殺人や復讐劇ではなく、宗教的かつ哲学的な問いを観客に突きつけました。なぜ彼はこのような犯行を企てたのか?その動機は理解不能な狂気なのか、それとも人間社会を映し出す鏡なのか。
本記事では、まず『セブン』の物語と七つの大罪の関係を整理し、次にジョン・ドウの行動やセリフを軸に犯行動機をじっくり考察していきます。
『セブン』のあらすじと七つの大罪
結末を含む物語の概要
雨の降りしきる無名の都市。退職間近の老刑事サマセットと、赴任したばかりの若き刑事ミルズは、猟奇的な連続殺人事件を追うことになります。被害者はそれぞれ「暴食」「強欲」「怠惰」「色欲」「傲慢」といった罪を象徴する形で殺されていました。
やがて姿を現した犯人ジョン・ドウは自ら出頭し、最後の二つの罪を完成させようと計画を明かします。砂漠に誘い出された刑事たちの前に届けられた箱の中身は――ミルズの妻トレイシーの首。ジョン・ドウは「嫉妬」に駆られてトレイシーを殺し、残る「憤怒」をミルズに背負わせることで七つの大罪を完成させたのでした。
七つの大罪と犯行の結びつき
ジョン・ドウの殺人は、単なる象徴的な遊びではありません。彼にとっては人間社会の罪を可視化する宗教的行為であり、「人間の愚かさを見せつけるための芸術作品」でもあったのです。
- 暴食:肥満男性を強制的に食べさせ続けて殺害。
- 強欲:金持ちの弁護士を自身の血で署名させ、命を絶たせる。
- 怠惰:麻薬中毒者を一年間ベッドに拘束、生ける屍にする。
- 色欲:売春婦を凶器で殺させる。
- 傲慢:美貌に執着する女性に「通報するか自殺するか」を迫り自害させる。
- 嫉妬:ジョン・ドウ自身が罪を体現し、ミルズの家庭を破壊する。
- 憤怒:ミルズがドウを撃ち殺すことで完成。
この構造そのものが、ジョン・ドウの世界観を理解する鍵となります。
ジョン・ドウの犯行動機を考察
「病んだ都市」に対する宗教的使命感
ジョン・ドウは劇中で「世界は腐敗し、罪に満ちている」と語ります。彼にとって犯行はただの犯罪ではなく、人類に対する「説教」でした。彼はあくまで自己犠牲を含めて七つの大罪を完成させることで、自らを宗教的な殉教者のような存在に高めていたのです。
この観点では、彼の動機は「正義の執行」すら自称するものであり、狂気と信念の境界線が曖昧になっています。
「理解されないこと」を前提にした芸術性
ジョン・ドウは「人々はこれを一週間は騒ぎ立てるだろうが、やがて忘れる」と語ります。つまり、自分の行為が普遍的な正義とされるとは思っていません。むしろ、忘れ去られることを前提に「一瞬でも社会に鏡を突きつける」ことに意味を見出しているのです。
この態度は芸術家のそれにも似ており、「犯罪を通じた表現者」としての側面が浮かび上がります。
嫉妬と人間的弱さ
最も重要なのは「嫉妬」です。冷徹に見えたジョン・ドウも、ミルズの家庭に憧れ、自分には持てない幸福を欲したという人間的弱さを抱えていました。ここに彼の犯行動機の核心があります。
彼はただの「冷酷なシリアルキラー」ではなく、最後の最後に人間臭さを露呈し、それをも自らの計画に組み込むことで「完全な構造美」を完成させたのです。
ジョン・ドウの動機から見えるテーマ
善悪の相対性
『セブン』が名作たり得る理由の一つは、犯人の動機が完全な狂気に留まらず、観客に「一理あるのでは?」とすら思わせる点です。もちろん彼の行為は許されない犯罪ですが、その根底にある社会批判は無視できないものがあります。
社会の腐敗と観客の不安
90年代のアメリカは暴力犯罪が増加し、都市の治安は悪化していました。映画の空気感はまさに当時の社会不安を反映しており、ジョン・ドウはその「不安の化身」として観客の記憶に刻まれたのです。
神の代理人か、ただの人間か
ジョン・ドウは自らを「神の代弁者」のように演出しますが、最後には嫉妬という人間的感情で計画を動かしました。ここにこそ本作の深みがあり、「彼は神ではなく、ただの人間に過ぎない」という皮肉が込められています。
まとめ
『セブン』におけるジョン・ドウの犯行動機は、一言で説明できる単純なものではありません。そこには宗教的使命感、芸術的表現欲求、そして人間的弱さが複雑に絡み合っています。
彼の行為は社会的に許されるものではなく、倫理的にも断罪されるべきものです。しかし、その狂気の中に人間社会の縮図や観客自身の不安が映し出されているからこそ、本作は公開から数十年経った今も語り継がれるのです。
映画ファンとして私たちが『セブン』を観返すとき、ジョン・ドウという存在は「ただの悪役」ではなく、「人間の罪深さを象徴する存在」として立ち現れてきます。そしてその動機を考え続けることこそが、この映画の本質的な楽しみ方なのかもしれません。




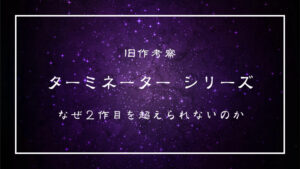




コメント