スティーヴン・スピルバーグといえば、『ジョーズ』『E.T.』『ジュラシック・パーク』『シンドラーのリスト』など映画史を変えてきた巨匠です。
しかしその長いキャリアの裏には、「企画されながらも実現しなかった作品群」が数多く存在します。
そこには他の監督に引き継がれ大ヒットした作品もあれば、幻に終わった野心的な企画もあります。
こうした「撮るはずだった作品」を振り返ることは、彼の作家性を別の角度から照らすことにもつながります。
スティーブン・スピルバーグが撮るはずだった映画
『レインマン』バリー・レヴィンソンに渡った名作
1988年のアカデミー賞作品賞を受賞した『レインマン』は、当初スピルバーグが監督する予定でした。
彼は脚本を読み、トム・クルーズやダスティン・ホフマンとも接触していたといいます。
しかし当時『インディ・ジョーンズ/最後の聖戦』に集中する必要があり、スケジュールの都合で降板。
結果的にバリー・レヴィンソンが監督を務め、名作として世に残ることになりました。
もしスピルバーグ版が実現していたら、よりドラマチックで感情の起伏が強調された作品になっていたかもしれません。
『ビッグ』ペニー・マーシャルが切り開いた青春
トム・ハンクス主演の1988年の大ヒット作『ビッグ』も、スピルバーグが監督候補に挙がっていました。
彼は企画段階で関心を持っていましたが、当時ファミリー映画が続いていたスピルバーグは「似たトーンの作品が多すぎる」と判断し、結局辞退。
後にペニー・マーシャルが女性監督として初めて1億ドルの興行収入を突破する快挙を果たしました。
スピルバーグが撮っていたら、ユーモアよりも「子供が大人の世界に放り込まれる怖さ」を強調していたかもしれません。
『ハリー・ポッターと賢者の石』子供時代の夢の城
実は『ハリー・ポッター』シリーズの映画化にあたり、ワーナー・ブラザースは最初にスピルバーグへ監督を打診しました。
彼自身も乗り気で、子役にハーレイ・ジョエル・オスメントを推していたと言われています。
しかし「アメリカナイズされすぎる」という懸念や、スピルバーグ自身が『A.I.』に集中したいという事情もあり辞退。最終的にクリス・コロンバスが監督を務め、世界的な現象となりました。
スピルバーグ版であれば、もっと壮大でダークなファンタジーになっていた可能性があります。
『インターステラー』ノーランへ託された宇宙
クリストファー・ノーラン監督の2014年作『インターステラー』は、実はスピルバーグが2000年代から携わっていた企画です。
科学者キップ・ソーンの理論に基づき、ワームホールとブラックホールを描く壮大なSF映画を構想していました。
しかし製作会社との契約やスケジュールの問題で降板し、その後ノーランに引き継がれました。
スピルバーグが監督していれば、科学よりも「人間ドラマ」に重点を置いた、より感情的な宇宙叙事詩になっていたかもしれません。
『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』
スピルバーグは長年ジョージ・ルーカスと親交が深く、『スター・ウォーズ』シリーズを手掛ける可能性が何度も浮上しました。
特に『ローグ・ワン』では製作段階でスピルバーグに白羽の矢が立ったとも言われています。
最終的にはギャレス・エドワーズが監督しましたが、もしスピルバーグ版が実現していたら、戦争映画的な重厚さよりも「仲間の絆」を強調した冒険活劇になっていたのではないでしょうか。
幻に終わった企画たち
- 『ナポレオン』
スタンリー・キューブリックが残した幻の脚本を映像化するプロジェクト。スピルバーグがドラマシリーズ化を構想しましたが、まだ実現していません。 - 『リンカーン』初期案
2012年公開の映画に先立ち、もっと早い段階から構想していましたが、脚本の方向性が定まらず長期停滞。 - 『Robopocalypse』
ダニエル・H・ウィルソンの小説を映画化する企画。発表までされたものの、製作費と脚本面の課題で延期され続けています。
スピルバーグは監督業だけでなくプロデューサー業にも力を注いでおり、同時進行する企画が常に10本以上あると言われます。
そのため「興味を持ったがスケジュールが合わない」「他の監督の方が適任」と判断して譲るケースが多いのです。
また、彼自身の作品観が「ファミリー」「人間ドラマ」「歴史」「冒険」と広範囲にわたるため、優先順位を決めざるを得なかったとも言えます。これらが実現に至らなかった背景に含まれていると言えるかもしれません。
まとめ
「スピルバーグが撮るはずだった作品」を振り返ると、そこには映画史の“もしも”が数多く潜んでいます。彼が監督していたら全く違う傑作になっていたかもしれませんし、逆に映画史に現存する名作が生まれなかった可能性もあります。
巨匠の未完プロジェクトは単なる幻ではなく、彼の作家性や時代との関わり方を映す「もうひとつのフィルモグラフィー」なのです。そしてそれを追うこと自体が、映画史を深掘りする楽しさのひとつだと言えるでしょう。
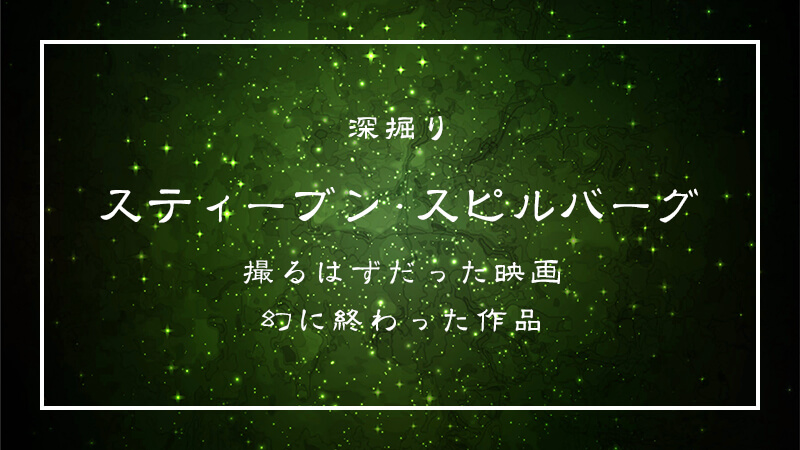
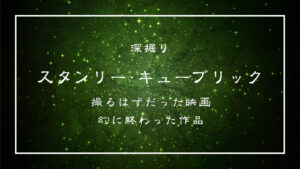
コメント